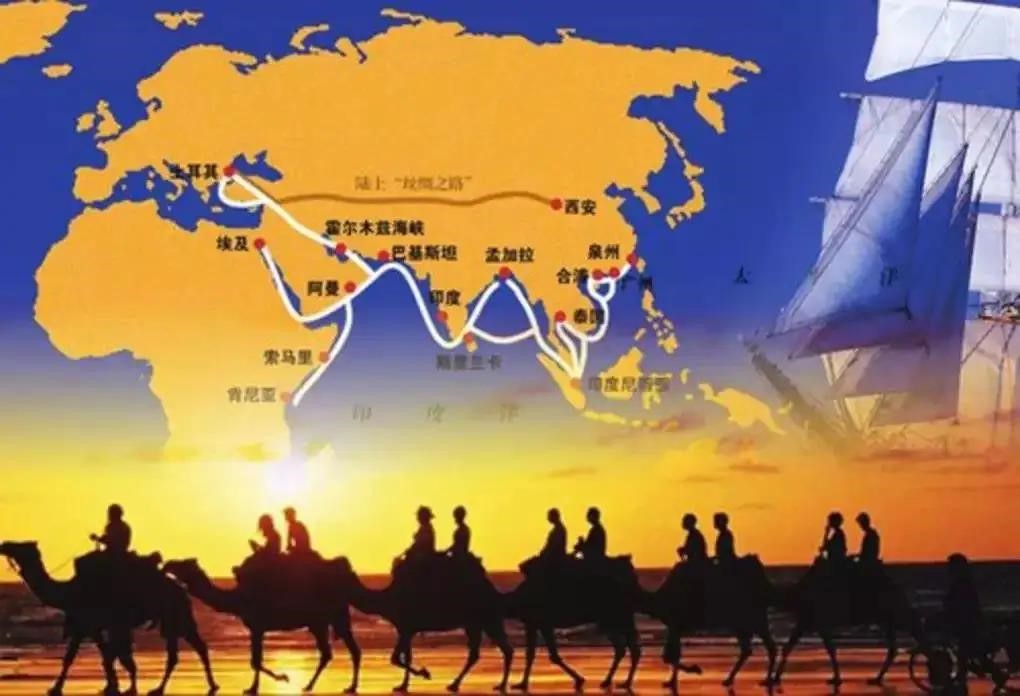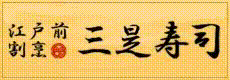コラム >> 石田隆至
2024/7/21コラム
沖縄では、「戦後」がよりはっきりとした形で続き、冷戦構造も継続している。近年では琉球弧の軍事要塞化も進んでいる。 そうした状況下でも、独自の平和追求の文化が静かに長く脈...
2024/6/24コラム
中国では近年、戦史研究が活発に進められている。戦闘だけでなく、戦時下の経済や社会、文化の実態についても若手研究者の関心が集まっている。過去の連載で取り上げた武凌宇もその一...
2024/5/21コラム
日本軍による侵略を経験した中国の民衆は、長い「戦後」を経て、今どんな思いで過ごしているのだろうか。 2023年12月、浙江省桐郷市で地元の戦史を掘り起こす調査研究を続け...
2024/4/23
戦後の平和教育といえば、広島・長崎の被爆体験が主に扱われてきた。繰り返してはいけない惨劇であることはいうまでもない。しかし、日本の枠を越えてヒロシマ・ナガサキを捉えるとき...
2024/3/21
私たちは当たり前のように「戦後」という枠組で “いま”を捉えている。これは奇妙なことではないだろうか。 対中国15年戦争が終わってからまもなく80年にもなる。新中国の建...
2023/12/23
侵略戦争への贖罪意識だけでは戦後生まれの世代には継承されにくい。“戦略的互恵関係”といったドライな理念は時の状況に簡単に翻弄されてしまう。日中関係を開く「鍵」は思いもしな...
2023/11/21
半年ほど前、自分が暮らす地域の戦時中の歴史に向き合う中国の青年と知り合った。若い世代が負の歴史に積極的に関心を持つのは、中国でも珍しい。経済成長が進んで自己実現の機会が高...
2023/10/26
現在の日中関係の焦点の一つは「台湾問題」にある。 これについて語るとき、必ず言及されるのが「一つの中国」という立場である。台湾を含めて中国は一つの主権国家であるという概...
2023/9/24
45年前、平和友好条約の締結に臨んだ人たちは、後に続く世代の日中関係をどう思い描いていただろうか。 筆者を含めた国交回復後に育った世代には、「日中友好」というフレーズは...
2023/8/28
近年、日中友好を掲げる運動の中にさえ「中国脅威論」の浸透を感じることがある。さすがに“中国は脅威だ、攻撃に備えよう”とまでは言わない。ただ、“中国は発展して大国になり、膨...
2023/7/26
「中国脅威論」が高まっている。とはいえ、中国に対する警戒感を持ってはいても、できれば日中関係を好転させたいと願っている人々は少なくないだろう。ましてや、中国を敵視する現状...
2023/2/25コラム
この秋、日本社会の戦争観に関する文献を中国の大学院生と輪読した。田中角栄元首相に関する受講生の反応が興味深かった。「私たちが受けた教育の中では、田中は中国への侵略だった...
2023/1/23コラム
前回取り上げた孟生保さん(83歳)は、戦争で失われた家族やその戦友たちの尊厳を取り戻すために戦後を歩み続けた。被害調査を続けるのが難しくなった2000年代には、高校生だっ...
2022/12/12コラム
国交回復によって戦争被害者とも向き合おうとすればできるようになった。そうした動きはどれくらいあっただろうか。これは無理筋な話ではない。日本社会には、原爆や空襲の被害者に対...
2022/11/25コラム
国交回復50周年を振り返り、新たな展望を考えていく上で、手がかりとなる文書が中国で先月発表された。第20回中国共産党全国代表大会の「報告」である。日本のメディアではその一...
コラム
 |
2024/7/19 |
|
 |
2024/7/21 |
|
 |
2024/7/22 |
|
 |
||
 |
2024/7/25 |
|
 |
2024/7/24 |