科学技術振興機構(Japan Science and Technology Agency、略称JST)は、日本の科学技術政策を推進することを目的として設立された文部科学省所管の国立研究開発法人である。変容著しい世界の科学技術を見据えながら、日本のイノベーションを推進先導する同機構の濵口理事長にその抱負を語っていただいた。

撮影/本誌記者 倪亜敏
科学技術の4つの役割
—— まず、科学技術振興機構の設立目的と主な取り組みについて教えていただけますか。
濵口 文部科学省の下で、いわゆる研究費を提供しているところは、日本学術振興会(Japan Society for the Promotion of Science 略称JSPS)と科学技術振興機構です。この2つは、役割が大きく分かれています。日本学術振興会ではキュリオシティ・ドリヴン(curiosity driven)、要するに研究者1人1人の「好奇心」をとても大事にしています。人間が持っている基本的な好奇心が原動力になって科学をつくっていく作業を、日本学術振興会はサポートしています。だから基本的には個人ベースで、研究者の純粋な気持ちが一義的な出発点になっています。
科学技術振興機構はそれとは少し違い、イシュー・オリエンテッド(issue oriented)と言って課題解決型です。これはJST単独の考えではなくて、社会の流れの中でみれば、結節点になるのが1999年の世界科学会議で採択された「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」、いわゆるブダペスト宣言です。そこでは、人類社会が21世紀を迎えるに当たって、科学技術には4つの役割があるということが明文化されました。1番目は「知識のための科学」で、これはキュリオシティ・ドリヴンと同じような意味です。2番目は「平和のための科学」で、3番目が「開発のための科学」です。それから4番目が「社会における科学と社会のための科学」です。JSTではその2番目・3番目にもある程度絡んでいますが、4番目の「社会における科学と社会のための科学」とは何かをずっと考え、取り組んでいます。そのためにいろいろな課題をもうけては、研究者を組織して、その人たちに研究費を提供し、課題を研究していただくということをやっているのです。代表的なものだと、量子コンピューターであったり、最先端技術で特殊な材料を開発するというところから、もっと普遍的な、生物学と化学とを融合した研究はどうやったらできるであろうかとか、そういうカッティング・エッジ(先端的)なことをやっています。
東日本大震災から学んだこと
濵口 一方で、この数年私たちは、2011年に起きた東日本大震災から多くのことを学んできました。JSTは現地の復興を科学技術を通じて援助するということを随分と考え、実行してきました。それは自然のメカニズムで地震や津波がどうやって起きるのかといった解明だけではなく、もう一歩市民生活へ踏み込んで、普通の人の普通の生活、その中にある幸せをどうやって科学技術で支えていくのかということでした。壊れてしまった地域社会の仕事をどうやって復興させるのかとか、福島の高校生はずっと自分の地元で勉強したいけれど本当に安全だろうかとか、それぞれのフェーズ(局面)でいろいろな課題がありました。その中で、われわれが一番学んだのは、教育はとても大切だということでした。
釜石市(岩手県)での話ですが、あんなに大きな地震が起こるとは誰も考えていなかった。1000年に一回のことだから、まさかこの私たちが生きているときに起きるとは、誰も思っていなかったわけです。あのエリアでは、何百年も前からたくさんの犠牲者が出ているし、どこまで津波が来たという記録もいっぱいありますから、みんな知識としては持っています。なのに、「まさか自分に」という気持ちが強かった。だけど、釜石市の小中学校ではJSTのサポートで、大学の先生が何年も前から、地震が起きて津波が来たら、とにかく全部放り出して、何も考えずに後ろの山へ登りなさいと教えて、練習してきたのです。そのこともあって、釜石市の小中学校では生徒の生存率が99.8%です。
そういう気持ちの問題をプリペアード・マインド(準備された心)と言うことができます。「幸運というのは準備された心に微笑む(英語:Chance favors the prepared mind 仏語:le hasard ne favorise que les esprits préparés)」というパスツールの言葉があって、科学の世界での大発見には、やっぱり神様が支えてくれているような瞬間があるのです。お前の目の前に大発見があるぞ、これをちゃんと見なさいと神様が微笑むときがあるのです。ところが気が付かないと、何も起こりません。
だから、幸福だとか幸せになる、豊かになる、お金持ちになるということだけではなくて、予想していなかったようなリスクだとか、ストレスだとか、起きるかもしれないことに対して私たちがどう向き合っていくかというときは、やはり小中学校のときからプリペアード・マインドを教えるような教育をしていかなければいけないというのが、われわれのやってきた活動の中で、教訓として残ったことでした。

ノーベル賞には適齢期がある
—— 21世紀における日本人のノーベル賞受賞者は18人(米国籍含む)で、毎年1人のペースです。先生が総長を務められた名古屋大学でも、6人の受賞者を輩出しています。なぜこれほど多くの日本人受賞者が出ているのでしょうか。
濵口 客観的なデータからお話しすると、ノーベル賞受賞には、結婚と同じで適齢期があります。大体30歳から40歳の間にいい仕事をした人がノーベル賞をもらう確率が高いのです。ノーベル賞の対象になった論文がいつできたかというのを調べると、そこがピークなんです。もう1つの特徴は、ノーベル賞をもらうきっかけとなった論文は、無名の雑誌に載ったものが多いということです。特に名古屋大学の場合は有名な『Nature』とか『Science』に載ったものは1本もありません。ですから最初はほとんどの人は論文に注目しません。なぜかというと、論文を読んでも、そんなことがあるはずがないと思うからです。例えば益川(英敏)・小林(誠)の素粒子の仕事は、素粒子がそれまで2つだと言われていたけれど、数学的に計算すると2つでは合わないので、6つで考えると計算が合うというものです。3倍ですから、常識を超えています。
赤﨑(勇)・天野(浩)の青色発光ダイオードの研究も、20世紀中に実現不可能だと言われていました。ですから、予算がなかった。初期の頃に使っていた機械は全部手製です。よその教室が捨てた機械をもらってきて、自分たちで機械をつくるんです。それでノーベル賞をとりました。とったきっかけになった研究は、天野さんがまだ25歳のときのものです。修士(マスター)の時代に窒化ガリウムの結晶を作りました。25歳のときに、彼は1500回も失敗しています。毎日毎日失敗して、でも諦めなかった。そしてpn接合という、いわゆる光るものにしたのが28歳のときです。なぜ「適齢期」があるかというと、若い人というのは恐れを知らない、失敗してもくじけない。これが大事なことです。
ただ、赤﨑さんという偉大な先生がいたからこそ、天野さんはずっとそれをやっていけました。赤﨑先生は窒化ガリウムが大事だというところで、全然ぶれなかった。大先生がいて、恐れずに突進していく人がいるという、この組み合わせが、名古屋大学の場合、うまくいっていたのです。失敗を失敗だと言える師弟関係が大事で、これはこうあるべきだと言ったら、科学は止まります。
中国では「メディチ効果」が始まっている
—— ところで先生は、現代の中国の科学技術をどう見ていますか。研究開発において、日本と中国の近いところはどんなところですか。
濵口 中国の科学技術の現状は、データを見ますと、非常に勢いがあり、イノベーションの活気にあふれています。これはすばらしいことで、ノーベル賞に近づいているとも言えます。
ルネサンスがどうやって生まれたかという研究に「メディチ効果」というのがあります。それはどういうものかというと、メディチ家がイタリアのフィレンツェにヨーロッパ中の天才(レオナルド・ダ・ヴィンチもその一人です)を集めて、狭い地域でいろんなことを競わせたのです。その中から新しい考え方や、科学の在り方みたいなものが生まれて、ヨーロッパはキリスト教社会から近代社会へと移行していったのです。中国では今、上海、深圳、香港などのエリアが、そういうような形を担っているように思います。中国の新しい時代をつくっていくエンジンになってきています。
ただ、その先にどういう豊かさの価値観を描いていくかという、もう1つ別の問題があります。最先端技術だけをずっと追っていったのが、一時期の日本でした。確かに最先端技術はたくさん生まれましたが、決してそれだけで、30年前、40年前と比べて幸せになったかというと、ちょっと分からない。
現代社会というのは、昔のドイツ語の言葉を使うと、ゲマインシャフト(共同社会)からゲゼルシャフト(利益社会)への転換です。つまり、伝統的な地域コミュニティーである農村社会から、都市の生活に移ってきて、個人は、自分の生まれたところや家族、近隣の中で自分というものができてくるのではなくなった。どこかの大学に入って、どこかの会社に入って、何をやっているかでその人の価値が決まってしまいます。自分の生まれてきたバックグラウンドを全部捨て去って、個人として生きていく世界に入っていくわけです。
近代的な自我としては、それは実はわれわれのある種の概念的な哲学的な理想だったと思います。だけど、この東京では、個人はかなり近代社会での孤独感を深くしている部分があります。それは北京を見ていても感じることです。この問題を、もっとみんなが冷静に議論をしていかなければいけません。
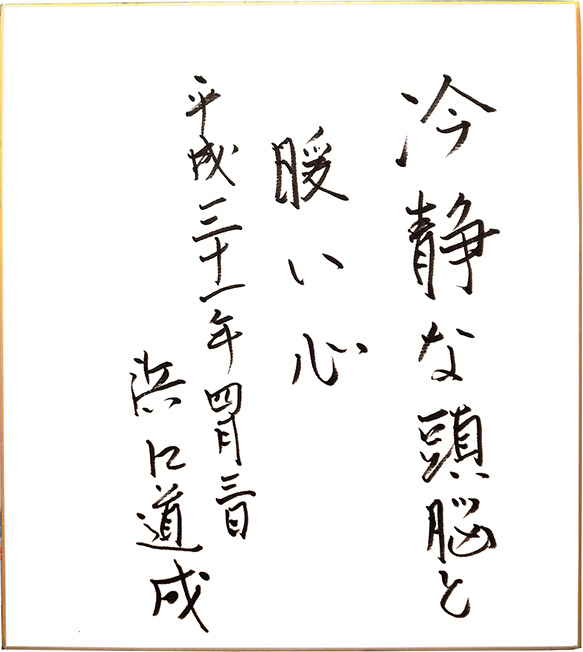
日中の交流は顔と顔が見える形で
—— 現在の中国と日本は経済の面でともに発展していますが、科学技術でもともに発展することはできるでしょうか。
濵口 もう少し顔と顔がつながるような関係をつくらないといけないと思います。1つの変化が2つの問題を生み出しているからです。1つの変化というのは、中国の発展が非常に早く、量的にもすごい量が動いていることです。上海も、最初に行った頃は地下鉄が1本しかなかったし、高速道路もなかったけど、今はすごいです。北京も最初に行ったときは、車が少なく自転車がいっぱい走っていました。真っ暗になってもみんな自転車を走らせて、本当に働き者だなと思い、印象深かった。その状況からずっと経って、今や世界最先端の科学技術開発ができるところまで来ています。
このギャップがどういう問題を生み出しているかというと、1つは古い日本人たちは、古い中国の記憶のまま、今も中国を見ているところがある。だからズレがあります。それから、若い中国の人たちは、日本と何かをやってきたという体験があまりなくて、アメリカを見ています。この2つのズレが、いろんな意味で中国と日本が一緒にやることの難しさになっています。それを越えるには、やはり顔と顔が見える形で、もっといろんな交流をするということが必要ですし、できる時代になってきていると思います。
トップニュース
 |
||
 |
2024/7/4 |
|
 |
||
 |
2024/7/1 |
|
 |
2023/10/5 |
|
 |
2023/10/12 |










