2015年3月、東京都豊島区に斬新なデザインのランドマーク「としまエコミューゼタウン」が誕生した。同年6月、完成からわずか3カ月でその不動産価格は24%上昇した。「としまエコミューゼタウン」のネーミングは日本語、フランス語、英語の単語を組み合わせたもので、ビルの本体は日本で唯一の、区役所、超高層マンション、商業施設が一つになった免震建築物である。この超高層ビルの外観デザインを監修したのが、日本の著名な建築家・隈研吾氏である。
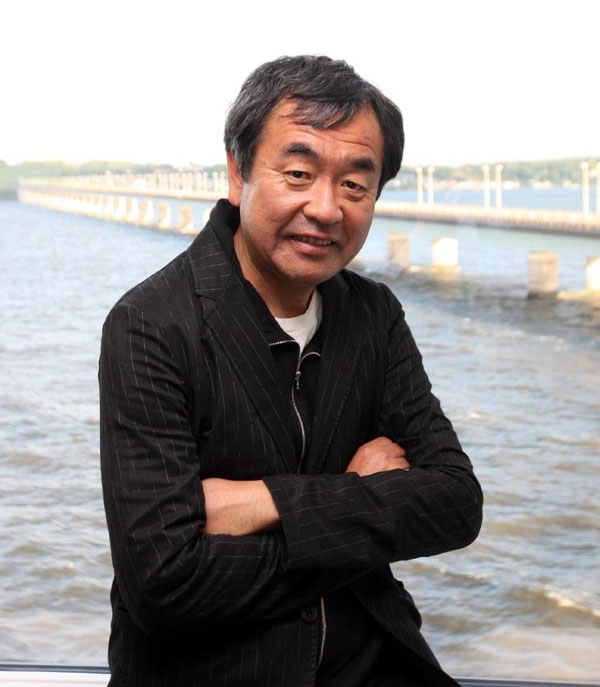
デビューは衝撃的
隈研吾建築都市設計事務所はアーティスト、文化人が集まる東京・南青山にある。アポイントをとった時間は夜10時であった。30数年の記者生活でこのように遅い時間を指定してきた相手はいなかった。事務所に向かう途中、建築家とライターとは夜中に仕事をするという共通点があると思った。夜10時はきっと隈研吾氏が仕事を始める時間なのだろうと。
氏の第一印象は、背が高い、ということだ。身長1メートル87センチだが、側にいても威圧感がない。彼は少々疲れた顔で、今仕事が終わったところですと言った。夜10時は仕事を終える時間だったのだ。
隈氏は東京大学大学院建築意匠専攻修士課程修了後、コロンビア大学の客員研究員として米国に渡り、36歳で帰国して事務所を設立した。その2年目に激烈なコンペを勝ち抜いてマツダ自動車のショールームのあるM2ビルの設計を担当、独自のイマジネーションでユニークなビルを創造した。正面中央にはふつうの柱の8倍のイオニア式円柱がある。このような大胆な建築は注目されるために生まれたと言えるだろう。
M2は議論を呼び、彼はいきなり日本を震撼させた。バブル経済崩壊にともない、M2もバブル建築の代表と目され、東京の建築界を追われた。12年間ものあいだ東京ではプロジェクトを請け負えなかった。
「マイナスの建築」理念
この12年間を隈研吾氏は感慨深げに振り返った。「あれは人生で最も低調な十数年でした。当時は東京で一つもプロジェクトを請け負えず、すべて地方の友人や知人に紹介してもらいましたが、その頃の経験が現在の私の最大の財産となっています。東京で設計に携わっている建築会社の社長は、時間と予算がすべてだと言います。地方で仕事をするなかで、直接職人さんたちといっしょに、どんな材料を選べば良いか、どのように使うかなどを話し合う機会が持てました。とても細かいところまで具体的な話をすることができました」。
刀鍛冶の名人は「人剣合一」を目指す。建築家は自らの心意気を建築物に込める。事務所を設立したばかりの彼は、唯我独尊、挑戦的な姿勢を明らかにし、M2 のような存在感を示した。
地方では自然を友とする「帰去来」の十数年間で、彼の建築は自然に合わせるように変わり、環境に溶け込み、シンプルにして深遠、淡泊にして味のある禅の境地を醸し出している。彼個人の建築理念と価値観は大きく転換し、西洋のモダニズム、ポストモダンの旗手に甘んじることなく、自身の風格を確立し、それを「負ける建築」と定義した。
「負ける建築」の「負ける」とは装飾過剰な建築から引き算をしていくことで、コンクリートの冷たい感じを弱め、建築物と周囲の環境との衝突を減らし、建築を脇役として環境への配慮を最優先させるという意味だ。同時に彼は、建築に木材、紙、竹などの天然素材、伝統的素材を使い、光と風と空気が建物内部を自由に流れるようにした。
例えば、浮世絵師・安藤広重を記念した那珂川町馬頭広重美術館は、屋根、壁はもちろん家具に至るまで、現地の特産である杉を使っている。建物全体が杉のルーバーに囲まれているが、ルーバーのサイズは精密に検討されて決められており、細部の光沢はそれぞれ異なっている。そこから一日のなかで光線の変化が生まれ、ルーバーのパターンと投影も変幻し続け、まるで光のセンサーのようだ。安藤広重は創作活動をしていた時、自然界の変化に注目し、光、風、霧など自然の要素を視覚表現へと転換させようとした。彼の設計は安藤広重の浮世絵と同じものを表現しようとしているのである。
内省的に自然環境を受け入れるようになった変化について、彼はこう分析している。「ポストモダン、モダニズムは、結局は西洋で流行した建築様式です。日本は明治時代から西洋を手本とし始め、建築様式もまた西洋に追随しました。しかし、現在の日本ではただ追随していくだけではなく、新しい価値観を求めるべき時代を迎えています。物質の豊かさの追求のために環境を破壊している現在の社会は伝統と自然をもっと大切にし、本来の自然な状態に戻るべきです。自分の国と地域の文化に注目すれば、多くの新しいデザインのインスピレーションをかき立てることができるのです」。
現在、彼はプロジェクトごとに長い時間を費やして周辺の環境と自然の風景を観察、研究し、そのうえでどんな材料を使うかを決め、最後に設計図を引くのである。
今後は中国人建築家の時代
隈研吾氏は中国にも多くの代表作があるが、万里の長城のふもとのホテル・竹屋The great(banboo)wallを設計する以前、彼の中国建築に対する印象はそれほど良くなかった。中国のどこに行っても欧米風の高層ビルがあふれていたが、それらはみな三流品だったからだ。
万里の長城のふもとの土地を観察し研究した際、彼はその土地の地面はデコボコで、遠くに連綿と山が続き、周囲には木々が雑に不規則に生い茂っており、家を建てるのに不向きであることに気づいた。しかし、万里の長城そのものは、ばらばらな起伏の山の尾根に建てられていたのである。
彼は、建築を環境に溶け込ませるため、意図的に整地せず、傾斜地をそのままにして建物を地中から生えてきたように見せた。建築材料にはまず竹を思い付いた。竹は中国特有のシンボルであり、彼は昔から晋代の「竹林の七賢」の話を知っており、竹と長城周辺の殺風景さとはよく調和すると考えた。
竹屋の設計で彼は光、影、風など自然な要素を応用した。竹屋のガラスと竹竿の隙間は太陽光を反射して多層に分かれ、光と影がつくりだす景観は時刻や季節により異なる。
竹屋の中から人は竹の隙間を透かして外界のすべてを見ることができる。浮世を見透かしながらも見限りはしない心境でなければ、このように自由で自然な建物を設計することは難しい。彼自身、「竹屋を気に入っていることは確か」だと言う。
中国で設計した建物のなかで一番気に入っているのは、杭州の中国美術学院美術館だと語る。中国美術学院美術館は茶畑が覆う山の斜面の上にあり、彼が一貫して大切にしている人間文化、土地への親しみ、環境との融合、自然との調和という建築理念によって、美術館を山の斜面に合わせ、山に寄り添わせて、外部と内部が相互に交わり流動する空間を作り出した。
建築材料も現地に捨てられた古い石瓦というリサイクル資源を使っている。高所から美術館全体を俯瞰すると、まるで鳥が茶畑をかすめ飛んでいるかのようである。
また、彼は中国が日本に遅れをとったため盲目的に西洋建築スタイルに追随する傾向を憂慮しており、こう話す。「今後は中国の建築家たちが大いに活躍する時代となるに違いありません。エネルギーに満ちたアイディアのある若い建築家に中国の代表的な建築物、国家プロジェクトを先頭に立って設計してほしいと思います」。

中国北京・三里屯SOHO
東京オリンピックが日本の若者を変える
5年後、東京で2回目のオリンピックが開かれる。隈研吾氏が建築家への道を歩んだのは、1964年の東京オリンピックがきっかけだった。当時まだ小学生だった彼は、父といっしょに丹下健三が設計したオリンピックのメイン会場である代々木体育館に行った。
まるで叙事詩のように優美で広々とした建物は、多感な少年の心に衝撃を与え、それまで獣医になりたいと思っていたが、心底敬服できる建築家という職業こそ素晴らしいと思うようになった。
隈氏の父は普通の会社員だったが、一番の趣味は自分で家を直すことだった。背が高い息子は良き助手となり、毎週末父親とともに木工をしたり、ペンキを塗ったりした。「小学生から始めて、中学生のころには自分ひとりでできるようになりました。父には本当にこき使われましたが、私と父の関係はそのおかげでとても近づきました」。
1964年の東京オリンピックは、隈少年の心に夢の種をまいた。その夢が実現した現在、彼は人生2回目の東京オリンピックを迎えるための準備をしている。「今、山手線の新駅の設計をしているところです。屋根からプラットフォーム全体が見えるのですが、日本の鉄道駅でこのような設計は初めてです。2020年の東京オリンピックでは駅前広場を使うと聞いています」。
東京オリンピックの意義は本当に大きいと彼は話す。そして、東京オリンピックがすべての日本の若者に大きな意義をもたらすことができるように願っている。
「1964年の東京オリンピックが日本の若い世代を奮い立たせ、若者に夢を追うチャンスと勇気を与えてくれました。私自身もその時に獣医にならずに建築家になろうと決意したのです。私は2020年の東京オリンピックが、現状に甘んじ内向的すぎる日本の若者がアクションを起こす契機になってほしいと思っています」。
としまエコミューゼタウンの初志
インタビューの最後に、としまエコミューゼタウンの住民として隈研吾氏に、なぜこのランドマーク的建築物の設計を引き受けたのか尋ねた。彼はこう答えた。
「商業施設、区役所、超高層住宅が一体となった新型の総合ビルを建設することは、豊島区長からの提案です。区長はビジネス界の出身で経済学的な思考で行動します。私がこのビルの設計を引き受けたのは、まさにその提案が新鮮でチャレンジ性を持っていたからです。一般に役所の建物はスタイルが重々しい傾向がありますが、私が得意とするのは小型建築の設計で、今回のような大プロジェクトは初めてなのです。そこで、重々しさを弱めるため、建物に多くの緑色を取り入れ、風の通り道をつくり、その中にいる人が鋼鉄の建物に閉じこめられたと感じないように設計しました。区長は特に、ビルの周囲の商業施設に影響が出ないように、ビルに出店する店舗が多くなりすぎないようにと注文をつけました。彼はそんなことまで考慮していました。ビルが完成した時、人びとが『こんな区役所は見たことがない』と言っているのを聞いて、大変うれしく思いました。私が求めていた結果が出たのです」。
取材後記
インタビュー終了後、隈氏は「アジアのパワー、自然のパワー!」と揮毫してくださった。これは彼のインスピレーションの根源である。そして今後のアジア建築学、経済学、社会学にとって、人間文化を重んじ、土地に親しみ、人のために着想し、自然と調和し、環境と相互に作用し、アジアの特色を維持し、アジアの特長を発揮するという努力をしていくべき目標なのである。
トップニュース
 |
||
 |
2024/7/4 |
|
 |
||
 |
2024/7/1 |
|
 |
2023/10/5 |
|
 |
2023/10/12 |










