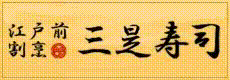1950年代
新中国成立初期、その頃は、北京、上海といった大都市を除き高層住宅はなかった。国民の大半は屋根の低い平屋建てに住んでいた。そして、その家は勤め先から供給されたものだった。当時は仕事も家も国家から“配分”されており、住居は勤め先から無償で割当てられていた。
1960年代
都市建設が順調に進み、住民は画一的だが住宅を持ちはじめた。しかし、国力がまだ弱かったので、住宅は依然として50年代の造りをそのままだった。長屋風の集合住宅が大半で、一軒に一部屋、五、六軒に一間の共同の台所、何棟かに住む数百人でひとつの共同便所を使っていた。
1970年代
「文化大革命」が終わり、政府の方針は「改革開放」、経済建設を中心とした政策に転換され、住民の住宅条件がいろいろと改善された。そして、中・小都市の住宅の変革が始まった。やっと台所・便所・寝室(居間)が一続きになった住宅があてがわれるようになった。それでも20平米そこそこの広さしかなく、いかにも狭かった。
1980年代
人々の生活水準は大きく向上し、住宅はすでに生活の質を高めるための重要な部分になりはじめ、ほとんどの家庭が平屋から鉄筋アパートや高層マンションに移り住むようになった。が、間取りの設計もいささか時代遅れの感があったし、占有面積も相変わらず狭かった。この頃から、住宅改革の試みが始まったが、共同住宅の構造、「福利分房」(勤務先が従業員に住宅を分配)という住宅政策、住み方は変わっていなかった。
1990年代
住宅建設のスピードが加速した。住宅設計は多様化し、メゾネット、スプリットレベル、庭付き一戸建てなどの住宅が出現した。1998年、数十年間にわたって実施されてきた「福利分房」制度が終わり、「貨幣分房」が実施されることになった。これで、商品住宅が認められ労働者が市場で住宅を購入できるようになった。国は三つの住宅供給制度を決めた。①高所得者は市場価格で住宅を購入できる(高級住宅:約1万人民元/㎡)②中・低所得者は経済力に見合った住宅を購入できる(一般住宅・マンション:約5000~1万人民元/㎡)③最低所得者は政府か勤務先が提供する安価な住宅を賃貸できる(経済適用住宅:約1500~4000人民元/㎡)というものだ。
21世紀
今日では次から次へと新しい方式の集合住宅が生まれている。最近は政府の指導もあって、高断熱、高気密化、環境・省エネ効果の高いハイブリット型の住宅まであらわれている。もちろん、都市には富裕層(4000万人~2億人)をターゲットにした高級別荘住宅もあれば、高級マンション、大規模ニュータウンもある。GDPで世界第2位に成長した中国は大都市の役割り、求心力が顕著になり、地方からの流入人口も増大している。当然、都市の住宅のニーズが劇的に拡大し、不動産業が内需を左右するまでになった。が、一部の都市の住宅価格はついに住民の購買力のレベルを超えてしまい、多くの人が住宅ローンに追われるようになった。
そして集合住宅では、昔の近所づきあいのにぎやかさは減って、同じく笑顔とあいさつが少なくなり、代わりに広々としたバルコニーと花壇の美しい風景が増えた。
(整理=趙展慧)
トップニュース
 |
||
 |
2024/7/4 |
|
 |
||
 |
2024/7/1 |
|
 |
2023/10/5 |
|
 |
2023/10/12 |